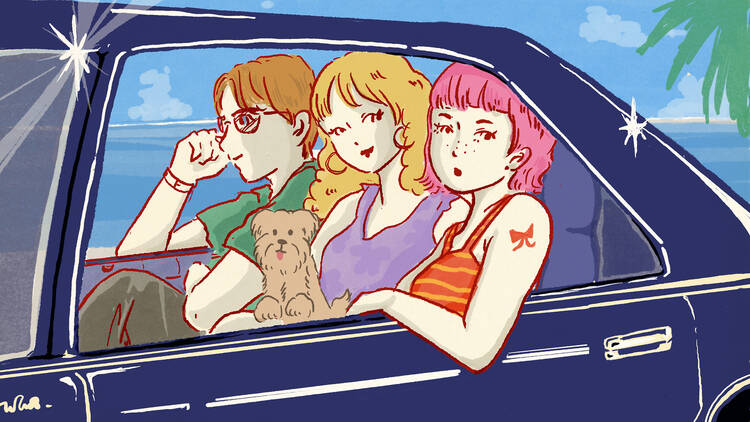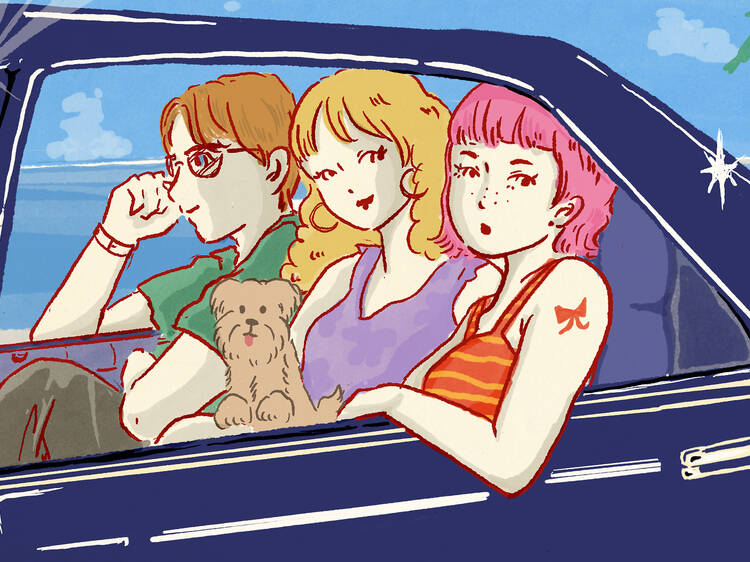1. 新旧さまざまな楽曲で踊れる


東京における盆踊りの特徴の一つが、かかる楽曲のヴァリエーションが豊かなことだ。
「東京音頭」「大東京音頭」など東京をモチーフにした楽曲のほか、ドイツのディスコグループであるボニーMの「Bahama Mama」など、盆踊りには一見ミスマッチに思える楽曲もかかる。
多くの地域で「ドラえもん音頭」などアニソン音頭も重要なレパートリーになっており、秋葉原を氏子地域の一つとする神田明神では近年「アニソン盆踊り」(2025年は8月8日に開催)と題する、アニソン音頭に特化した盆踊りが人気を集めている。毎年「クックロビン音頭」や「おそ松くん音頭」などで大変にぎわう。
東京は、戦後になって県外から多くの人々が流入し、多様なルーツを持つ住民による新たなコミュニティーが形成されてきた。そうした住民をまとめるため、流行歌や「アニソン」という共通言語による「新たな祭り」が必要とされてきた面がある。
東京の盆踊り曲の多様さは、そうした背景を現代に伝えるものともいえるだろう。