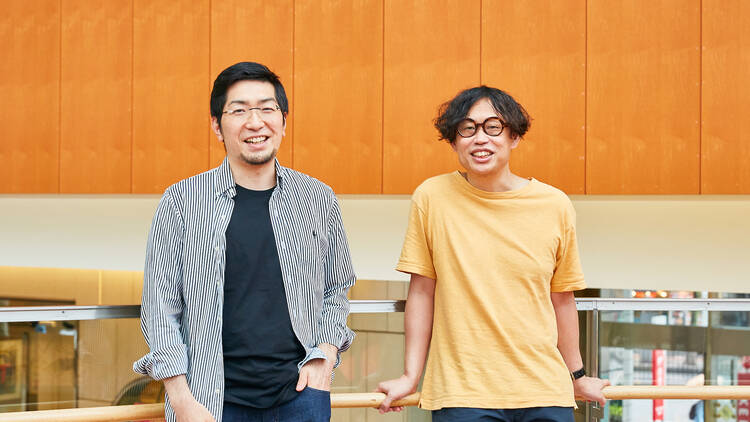今こそ2020年以前と以後を考える時期


―今回、高橋さんを含む現代のクリエーター、アーティストの皆さんが、「2020年」を起点とした作品づくりに注目しています。高橋さんご自身はどのような思いで、企画に関わられたのでしょうか。
かねてから、僕は上田さんの本が好きで親交もあり、その世界観と白井さんの演出が合うだろうと思っていたんです。上田さんが僕の舞台を観に来てくださった時に、白井さんと喋る機会はあったものの、じっくりお話しされたことはなかったので、お二人の話を聞いてみたいと考え、家に招きました。
その時は食事をしながら、「いつか何か面白いものがやれたらいいですね」という感じの話をしたのですが、その後、白井さんが少しずつ動いてくださり、本格的に上田さんと企画を立ち上げようと、パルコのプロデューサーの方に持ちかけてくださって。そこから「こういう話をやろうと思うんだけどどう?」と聞かれ、「おお、結構進んでいますね!」となりました。
―新型コロナウイルスのパンデミックが始まった2020年は、歴史の転換点だと思います。これが題材になったのは偶然なのか、それとも必然だったのか、どう思われますか?
お二人を家でお引き合わせしたのが2019年頃。つまり、こういう世の中になってしまう前だったので、意図していたわけではないです。ただ、企画をスタートさせましょうと言って皆さんとお会いをした時、2020年の出来事は僕たちにとって避けて通れないことだという話になった気がします。僕自身もそこに問題意識を抱いていましたし。
―避けて通れないというのは、パンデミック下での体験ゆえですか?
はい。あの状況の中で、少しはみ出したことを言ったりやったりする人に対して、抑え込む力のようなものが働くのが、正直なところとても気持ち悪かったんです。
リモートワークなど仕事の形態が変わり始めて、出向くことが省略できるようになったのは良い一面があったのかもしれませんが、どこを省略する、しないの線引きがいまだにはっきりしていないと感じています。会わなくて済むから便利な面がある一方、人と人が対面しなければという気持ちが個人的にはありますし、人の顔、表情が見られなくなったことの影響はかなり大きかったです。
―マスクのことですね?
ええ。例えば、俳優として現場にいると、最初のお客さんであるはずのスタッフの方々の鼻から下が見えないのはけっこう痛手で。お芝居を作っている時に他者に見てもらい、そのリアクションを受けて作っていくという、これまで大事にしていたことが根本的に塗り替えられてしまいました。こういうことは僕らの職業だけではなく、さまざまなところで起こっている問題ではないでしょうか。
だからこそ、2020年以前と以後のこの世界を、もう一回見つめ直したいという気持ちがあったんです。観ている人に何かを訴えたいということではなく、一度立ち止まって整理するという時期に来ているのではないか、と。