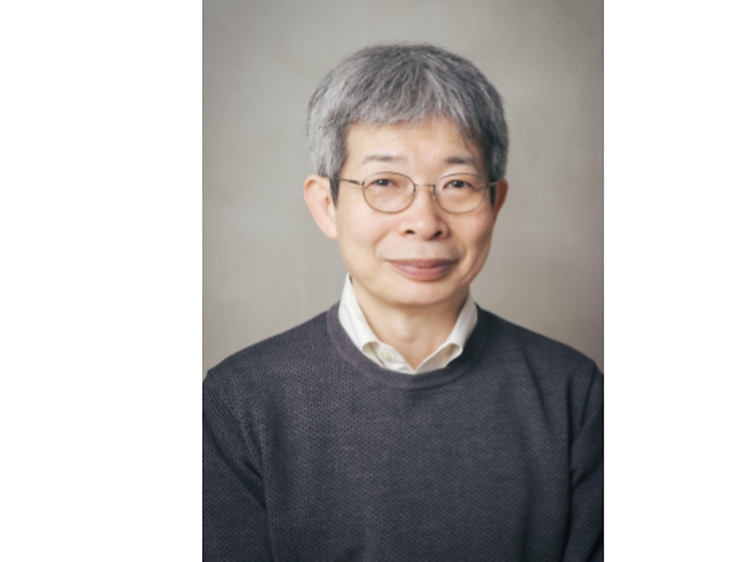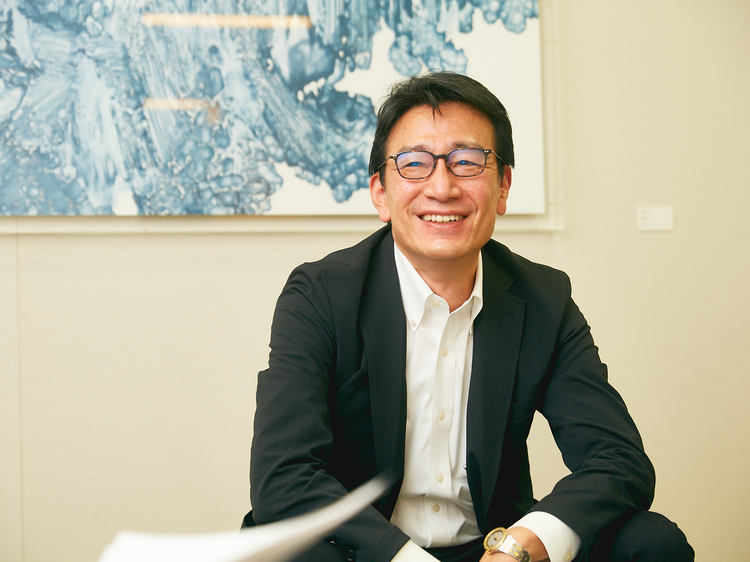『芸術立国論』のころは人の痛みが分かっていなかった
―平田オリザさんは、2001年のご著書『芸術立国論』以来、日本における芸術文化の在り方についてさまざまなご指摘やご提案をされてきました。『劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(劇場法)』の制定や、各自治体でのアーツカウンシル設立の流れなど、そのうちのいくつかは現実のものとなっているように思います。『芸術立国論』出版からちょうど20年がたちますが、その達成度において満足している点や、「ここはまだまだ」という部分があれば教えてください。
満足とか不満という感覚はないですね。私は政治家でも社会運動家でもなくアーティストですから、与えられた環境のなかで活動しますし、だめなら亡命するとか(笑)。文化政策に関することは、たまたま大学でそういう授業を受け持っているとか、もっと言うと各自治体からお願いされるからやってきたことであって、演劇そのもの以外のことで自分からやりたくてやったことは一つもないので。
それを前提に話すとすれば、もちろん想像通りになった部分と想定外の部分とがあって、『芸術立国論』のことで言えば、若かったこともあって「人の痛みがまだ十分には分かっていなかったな」という感じはあります。産業構造の転換は避けられないから第三次産業を核として、その基礎研究である文化芸術に力を入れないと日本という国は立ち行かなくなる、という理屈としては当然のことを今も昔も言ったり、書いたりしています。ですが、やっぱり製造業に就いている人たちの「寂しさ」のようなものについて、『芸術立国論』ではあまり触れていなかったですね。
―産業転換に付随する「寂しさ」のようなものというと、炭鉱の町だった福島県いわき市の実話をもとにした映画『フラガール』や、やはり石炭産業の終わりとともに衰退する町を描いた英国映画『ブラス!』などを例に出しながら『芸術立国論』以降の文章で積極的に言及している点ですね。
そうですね。そういう状況は、その後の小泉内閣による構造改革でより進むわけだけど、小泉さんは「改革には痛みが伴う」と、その「痛み」がどういうものかも考えず無邪気に発言してきました。その「痛み」の本質というのが、実は精神的な痛みなんだということを『芸術立国論』以降、いろいろなところで書いてきました。『ポリタス』に寄稿した記事『三つの寂しさと向き合う』などがその代表です。
日本はもはや「工業立国ではない」「アジア唯一の先進国ではない」「高度経済成長はない」ということ、その「寂しさ」を受け入れられない人が一定数いるんだ、そことも寄り添っていかなければならないということを誰よりも書いてきたつもりだったんですが、コロナのことで人の気持ちがさらにささくれて、私の発言さえも昨年炎上するということがありました。
―『フラガール』の福島県いわき市の場合は成功例として語られますが、炭鉱ということでいうと早くも1950年代前半には閉山ラッシュによる「戦後最初のリストラ」とも呼ばれる鉱山労働者の大量解雇があり、その後には文字通り村一つが丸ごとなくなってしまうことすら実際に起こっています。産業構造の転換というのがそれだけ影響力の大きなものであることを踏まえた上で、コロナ禍におけるさまざまな支援制度の対象が第二次産業を中心としたものになっていて、現状に即していないというご発言だったと理解しています。
エコノミストが当たり前のように言っていることでも、当事者の芸術家が言うと理解してもらえない。産業構造の変化に伴う「寂しさ」については私が最も言ってきたつもりだったんですが、社会の分断が思った以上に進んだということでしょうね。こうなってしまうと、もはや理屈ではない。要するにトランプ支持者と同じで、取り残されていく感覚を持った人たちが、実際には自分の利益と反する行動をどうしても取ってしまうという構造ですね。